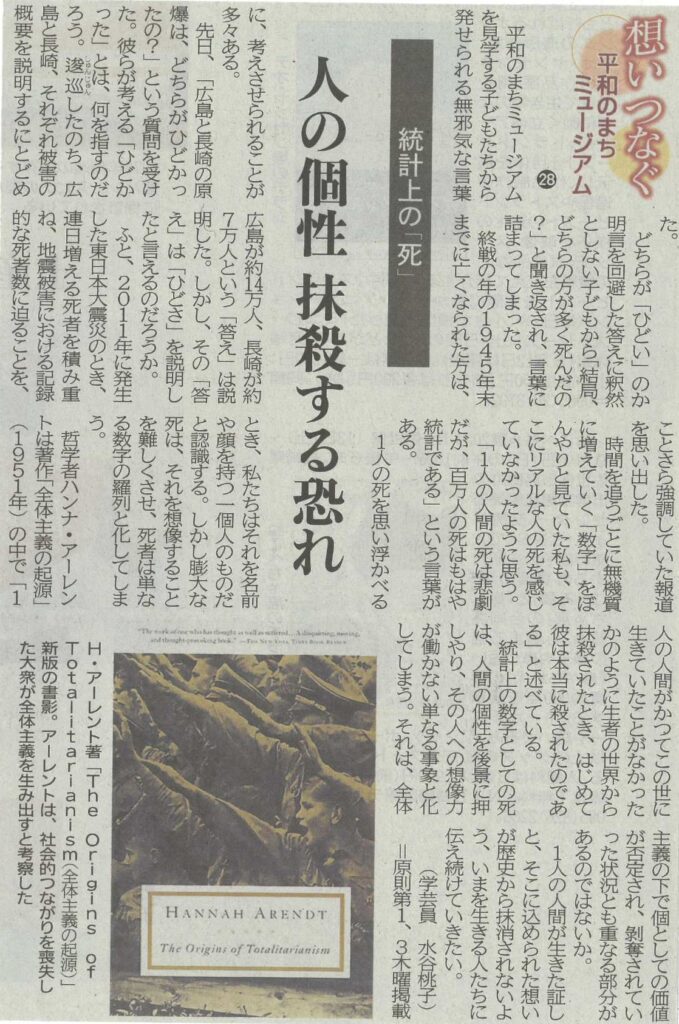番外編16「人の個性 抹殺する恐れ 統計上の『死』」
連載コラム『想い つなぐ』
★西日本新聞 北九州・京築版 2024年7月4日(木)朝刊16面掲載★
平和のまちミュージアムを見学する子どもたちから発せられる無邪気な言葉に、考えさせられることが多々ある。
先日、「広島と長崎の原爆は、どちらがひどかったの?」という質問を受けた。彼らが考える「ひどかった」とは、何を指すのだろう。逡巡したのち、広島と長崎、それぞれ被害の概要を説明するにとどめた。
どちらが「ひどい」のか明言を回避した答えに釈然としない子どもから「結局、どちらの方が多く死んだの?」と聞き返され、言葉に詰まってしまった。
終戦の年の1945年末までに亡くなられた方は、広島が約14万人、長崎が約7万人という「答え」は説明した。しかし、その「答え」は「ひどさ」を説明したと言えるのだろうか。
ふと、2011年に発生した東日本大震災のとき、連日増える死者を積み重ね、地震被害における記録的な死者数に迫ることを、ことさら強調していた報道を思い出した。
時間を追うごとに無機質に増えていく「数字」をぼんやりと見ていた私も、そこにリアルな人の死を感じていなかったように思う。
「1人の人間の死は悲劇だが、百万人の死はもはや統計である」という言葉がある。
1人の死を思い浮かべるとき、私たちはそれを名前や顔を持つ一個人のものだと認識する。しかし膨大な死は、それを想像することを難しくさせ、死者は単なる数字の羅列と化してしまう。
哲学者ハンナ・アーレントは著作「全体主義の起源」(1951年)の中で、「1人の人間がかつてこの世に生きていたことがなかったかのように生者の世界から抹殺されたとき、はじめて彼は本当に殺されたのである。」と述べている。
統計上の数字としての死は、人間の個性を後景に押しやり、その人への想像力が働かない単なる事象と化してしまう。それは、全体主義の下で個としての価値が否定され、剥奪されていった状況とも重なる部分があるのではないか。
1人の人間が生きた証しと、そこに込められた想いが歴史から抹消されないよう、いまを生きる人たちに伝え続けていきたい。