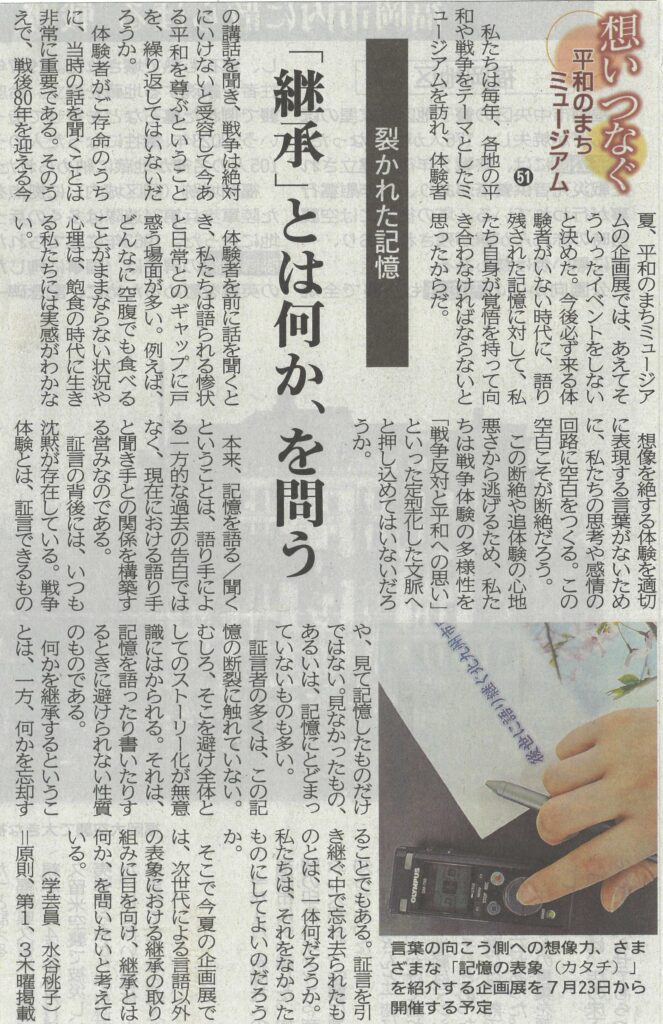番外編18 「『継承』とは何か、を問う 裂かれた記憶」
連載コラム『想い つなぐ』
★西日本新聞 北九州・京築版 2025年6月19日(木)朝刊14面掲載★
私たちは毎年、各地の平和や戦争をテーマとしたミュージアムを訪れ、体験者の講話を聞き、戦争は絶対にいけないと受容して今ある平和を尊ぶということを、繰り返してはいないだろうか。
体験者がご存命のうちに、当時の話を聞くことは非常に重要である。そのうえで、戦後80年を迎える今夏、平和のまちミュージアムの企画展では、あえてそういったイベントをしないと決めた。今後必ず来る体験者がいない時代に、語り残された記憶に対して、私たち自身が覚悟を持って向き合わなければならないと思ったからだ。
体験者を前に話を聞くとき、私たちは語られる惨状と日常とのギャップに戸惑う場面が多い。例えば、どんなに空腹でも食べることがままならない状況や心理は、飽食の時代に生きる私たちには実感がわかない。
想像を絶する体験を適切に表現する言葉がないために、私たちの思考や感情の回路に空白を作る。この空白こそが断絶だろう。
この断絶や追体験の心地悪さから逃げるため、私たちは戦争体験の多様性を「戦争反対と平和への思い」といった定型化した文脈へと押し込めてはいないだろうか。
本来、記憶を語る/聞くということは、語り手による一方的な過去の告白ではなく、現在における語り手と聞き手との関係を構築する営みなのである。
証言の背後には、いつも沈黙が存在している。戦争体験とは、証言できるものや、見て記憶したものだけではない。見なかったもの、あるいは、記憶にとどまっていないものも多い。
証言者の多くは、この記憶の断裂に触れていない。むしろ、そこを避け全体としてのストーリー化が無意識にはかられる。それは、記憶を語ったり書いたりするときに避けられない性質のものである。
何かを継承するということは、一方、何かを忘却することでもある。証言を引き継ぐ中で忘れ去られたものとは、一体何だろうか。私たちは、それをなかったものにしてよいのだろうか。
そこで今夏の企画展では、次世代による言語以外の表象における継承の取り組みに目を向け、継承とは何か、を問いたいと考えている。